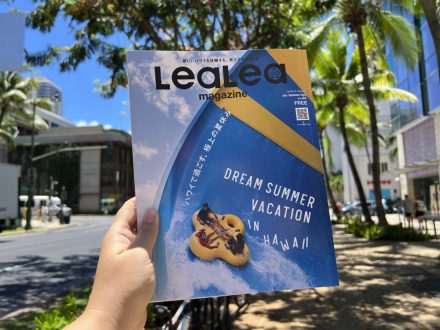アラモアナとワイキキの間を行き来する際、皆さまも一度は目にしているアラワイ運河。昼間は木陰でのお散歩が気持ちよく、サンセットや少し暗くなってからは夜景がロマンチックですよね。
昨年、1921年の建設開始から100周年を迎えたアラワイ運河ですが、かつては人が泳げるくらいきれいな水質だったのをご存知でしょうか?

今日では、運河で釣りを楽しむ人の姿は見かけても、泳いでいる人はまず見ません。では、何故そこまで水質が低下してしまったのでしょう?
建設当時の都市計画は、その後のワイキキの発展や上流地域の人口増加を予測するものではなかったというのが大きな原因の一つとして挙げられるようです。そのため、マノア、パロロ、マキキ地区の排水路であるアラワイ運河には、泥やゴミ、汚染源が長年蓄積されるようになってしまいました。

アラワイとはハワイ語で「水路」を意味します。アラワイ運河はその名の通り山から海へと水を運び、アラワイ・ハーバーを通ってマジックアイランドのダイヤモンドヘッド側の海に注いでいます。そのため、2006年の豪雨で下水管が破裂した際は、大量の下水が運河に流入、運河に溜まった未処理の下水が海に流出し、高濃度のバクテリアが発生して、ワイキキやアラモアナビーチが遊泳禁止になったこともありました。

そこで、自分たちが汚してしまった運河を次世代のためにも自分たちできれいにしようと声を上げ、動き始めたのが非営利団体「ゲンキ・アラワイ・プロジェクト」です。2019年に発足した同プロジェクトでは、沖縄県の琉球大学で開発された「EM(有用微生物群)」という善玉菌の集合体を使用して河川や自然を浄化し、「7年でアラワイ運河を泳げる水質にしよう!」という目標を掲げています。これまでに、地元の学校の科学教育に採用され、主にアラワイ運河付近の小学校とそのEMを入れた泥団子「ゲンキボール」を作って運河に投入する活動を展開しています。

「ゲンキボール」に使用される「EM」とは、琉球大学の比嘉 照夫名誉教授によって発見された技術です。長年農薬によって悩まされていた比嘉教授が、作物栽培のための微生物混合を研究する15年に及ぶ歳月の中で、偶然に発見されたのだとか。大阪の道頓堀川もEMで浄化されたというから、その効果は既に折り紙つき。ハワイの自然を守る技術に日本の力が関わっているというのは、やはりうれしいですし、誇らしいですね。
長く続いたコロナ禍での規制が緩和し、大人数の集会が可能になった今年の春頃から地元の企業や団体の支援も受け、「ゲンキ・アラワイ・プロジェクト」はその活動を活発化させています。4月には社会奉仕団体「ロータリークラブ」と5,000個のゲンキボールを作りアラワイ運河に投入したところ、2カ月間で運河のヘドロを15センチ以上減らすことができたとのこと。5月にも「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ワイキキ・ビーチ」と1,000個以上のゲンキボールを作り、動画のように投入したばかりで、そのさらなる効果が期待されます。

ハワイの伝統文化と美しい自然環境を守っていくための思いやりの心「malama / マラマ」を体現したこの「ゲンキ・アラワイ・プロジェクト」。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標として、世界でSDGs(持続可能な開発目標)が謳われるようになって久しいですが、ハワイの地元コミュニティに根差しつつ、目標達成に向けてその活動を加速させている同団体とコミュニティから生み出される絆や自然とのハーモニーも期待されます。大好きなハワイがこれからもずっとハワイらしくいられるように、自分の生活も見直したいと思う一日でした。
<2022/06/25の情報です>